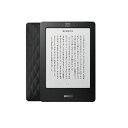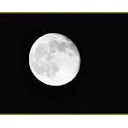気になって、著書を読んだりしたらなんだかますます気になってしまった。この気になり具合はどうにも言葉で整理できない、もやもやとしたもので、ならば体験してきましょうということで、甲野善紀さんの稽古会にお邪魔してきた。
http://www.dailymotion.com/video/xnenqu_yyyy-yyyy-yyyyy_tech
この動画で紹介されている技をひと通り体験させていただいた。
体験してみて、なんだかもの凄く心地の良い混乱がいまも続いている。
自分の意に反して身体が起こされているというのに、身体に負荷がかかる感覚がまったくなくて、動画の中で爆笑問題のひとりが言っているように「ふっときちゃう」のだ。
え?と思う。狐につままれたよう。なんか笑っちゃうしかない心地良さがある。
そして、この技。達人でなければ使えないというものではなく、手と指の使い方を教えてもらっただけで私にも出来てしまう、といのが驚く。実際にやってみたのは、膝を立てて座っている人を立たせる、というものだったのだけれど、立たせられた相手も、立たせた私も「え?」と思う。
意識したのは親指の使い方と腕の形、上体の使い方。で、力を入れたという感覚は一切なく、ふっと立っている、立たせている。
すごく混乱する。ワクワクするような混乱。この身体感覚は、いままで体験したことのないものだ。でも、これは自分の身体が目覚めるような、身体と一緒に意識も目覚めるような、そんな予兆に満ちた混乱。
革命といっていいのかもしれないなぁ。
http://www.dailymotion.com/video/xnenqu_yyyy-yyyy-yyyyy_tech
この動画で紹介されている技をひと通り体験させていただいた。
体験してみて、なんだかもの凄く心地の良い混乱がいまも続いている。
自分の意に反して身体が起こされているというのに、身体に負荷がかかる感覚がまったくなくて、動画の中で爆笑問題のひとりが言っているように「ふっときちゃう」のだ。
え?と思う。狐につままれたよう。なんか笑っちゃうしかない心地良さがある。
そして、この技。達人でなければ使えないというものではなく、手と指の使い方を教えてもらっただけで私にも出来てしまう、といのが驚く。実際にやってみたのは、膝を立てて座っている人を立たせる、というものだったのだけれど、立たせられた相手も、立たせた私も「え?」と思う。
意識したのは親指の使い方と腕の形、上体の使い方。で、力を入れたという感覚は一切なく、ふっと立っている、立たせている。
すごく混乱する。ワクワクするような混乱。この身体感覚は、いままで体験したことのないものだ。でも、これは自分の身体が目覚めるような、身体と一緒に意識も目覚めるような、そんな予兆に満ちた混乱。
革命といっていいのかもしれないなぁ。
いま一番気になるひと
2012年9月17日 日常 コメント (2)
甲野善紀さんと、甲野さんの行っている身体術、というものが気になっている。
子供の頃からスポーツは得意だ。
走る、跳ぶ、飛ぶ、飛び込む、投げる、打つ、撃つ、捕る、泳ぐ、潜る、よじ登る・・たぶんたいていのことは楽にこなせた。
もちろん競技者として生きるには、根気や欲や持続力や、欠けているものがいっぱいあるので無理だけれど、スポーツを楽しむ一般人としては、私は、とてもよく動く身体を持っていると思う。
いや、持っていた。
若く柔軟な身体を持っていた頃は、身体は勝手に動いていた。少しイメージしてやれば上方修正も簡単だった。40代になって、そうはいかなくなった。うっかり動くと捻ったり筋に痛みが走ったりする。5年前に自転車で転んで骨折したときには、歳をとるってこういうことなんだなぁと思った。
身体が若さに溢れていたころは、「身体を操縦する」なんて考えたこともなかった。身体は自由自在に動いたんだから。
自分の身体がままならなくなってみて、「身体を装置化する」という考え方と、そうして得られる身体感覚に触発されるであろう思考というものに、いまとても興味がある。
子供の頃からスポーツは得意だ。
走る、跳ぶ、飛ぶ、飛び込む、投げる、打つ、撃つ、捕る、泳ぐ、潜る、よじ登る・・たぶんたいていのことは楽にこなせた。
もちろん競技者として生きるには、根気や欲や持続力や、欠けているものがいっぱいあるので無理だけれど、スポーツを楽しむ一般人としては、私は、とてもよく動く身体を持っていると思う。
いや、持っていた。
若く柔軟な身体を持っていた頃は、身体は勝手に動いていた。少しイメージしてやれば上方修正も簡単だった。40代になって、そうはいかなくなった。うっかり動くと捻ったり筋に痛みが走ったりする。5年前に自転車で転んで骨折したときには、歳をとるってこういうことなんだなぁと思った。
身体が若さに溢れていたころは、「身体を操縦する」なんて考えたこともなかった。身体は自由自在に動いたんだから。
自分の身体がままならなくなってみて、「身体を装置化する」という考え方と、そうして得られる身体感覚に触発されるであろう思考というものに、いまとても興味がある。
ファゲ ギリシャヨーグルト
2012年9月13日 日常 コメント (2)
輸入食品を多く扱うマーケットで見かけて買った。
170gで570円のヨーグルトなんて普段は買わないのだけれど、去年の今頃、はにゃさんのところで「パルテノ」が紹介されていて、ギリシャヨーグルトが気になってたんだろうなぁ。
これを食べてみて、みなさんが、国産のプレーンヨーグルトを一晩水切りしてまで食べる気持がわかりました。
美味しいもの。美味しい!
でも高い!(笑)
これがチーズなら高いとは思わないけど、ヨーグルトで170gは食べ切りサイズだもんね。
でも美味しい!
んで、翌日、さっそく500g148円のPBのプレーンヨーグルト買って水切りしましたとも!
170gで570円のヨーグルトなんて普段は買わないのだけれど、去年の今頃、はにゃさんのところで「パルテノ」が紹介されていて、ギリシャヨーグルトが気になってたんだろうなぁ。
これを食べてみて、みなさんが、国産のプレーンヨーグルトを一晩水切りしてまで食べる気持がわかりました。
美味しいもの。美味しい!
でも高い!(笑)
これがチーズなら高いとは思わないけど、ヨーグルトで170gは食べ切りサイズだもんね。
でも美味しい!
んで、翌日、さっそく500g148円のPBのプレーンヨーグルト買って水切りしましたとも!
映画館で観るのは何年ぶりかな。
ぽっかり空いてしまった時間に、上映時間がぴったりだったので目の前にあったシネマコンプレックスへ入った。レディースデイだったし。
フランス映画だからかしらね、過剰なドラマもわざとらしいヒューマニズムもなくて良かった。映画の中にすっと入って、すっと出てきた。
.................
知人がこの映画を観てきたという。フランス語が堪能な人で、日本語字幕には訳されていない部分がいっぱいあったという。かなり下品な単語や台詞だそうだ。確かに、介護士の青年、クレバーなのはいいとして、クラスの違いを考えるとお行儀悪くないじゃない?と思った。言葉には、でるもんだよね。
上手い訳語がなかったのか、下品すぎて翻訳しなかったのか。どっちにしても、残念。
元の言語を知らないと理解できないニュアンスとかいっぱいあるんだろなーと、翻訳作品を読んで、観て、残念な気持になるとき。
ぽっかり空いてしまった時間に、上映時間がぴったりだったので目の前にあったシネマコンプレックスへ入った。レディースデイだったし。
フランス映画だからかしらね、過剰なドラマもわざとらしいヒューマニズムもなくて良かった。映画の中にすっと入って、すっと出てきた。
.................
知人がこの映画を観てきたという。フランス語が堪能な人で、日本語字幕には訳されていない部分がいっぱいあったという。かなり下品な単語や台詞だそうだ。確かに、介護士の青年、クレバーなのはいいとして、クラスの違いを考えるとお行儀悪くないじゃない?と思った。言葉には、でるもんだよね。
上手い訳語がなかったのか、下品すぎて翻訳しなかったのか。どっちにしても、残念。
元の言語を知らないと理解できないニュアンスとかいっぱいあるんだろなーと、翻訳作品を読んで、観て、残念な気持になるとき。
盆棚に飾ってみると、ほんとうに、ぽっと紅く燈った小さな提灯のようでかわいらしいし、なにやら精霊と相性も良さげに見えるものだな。
ほおずき、というものを初めてじっくりと見てみたような気がする。
東京は7月盆が普通だけれど、祖父母の家で迎えたお盆は8月だったし、父の葬儀が8月15日だったので我が家のお盆は旧盆で。先週、一周忌法要も行って、今日、新盆のお迎えをした。
父がほおずき提灯ぶら下げて歩いている姿を見たことがあるような、そんな気さえする。
ほおずき、というものを初めてじっくりと見てみたような気がする。
東京は7月盆が普通だけれど、祖父母の家で迎えたお盆は8月だったし、父の葬儀が8月15日だったので我が家のお盆は旧盆で。先週、一周忌法要も行って、今日、新盆のお迎えをした。
父がほおずき提灯ぶら下げて歩いている姿を見たことがあるような、そんな気さえする。
青空文庫で「蒲団」を読んでみた。
近代ブンガクの落とし穴にはまった感じ。
文学史に興味がないのでよく知らなかったのだけれど、自然主義ってなんなんだ?赤裸々、告白、暴露のことか。
もう、ほんと脱力した。
そりゃ、当時の人はさぞかし吃驚したろうと思う。書いた者勝ちだね。作品の、いままで誰も書かなかった「スタイル」だけで、文学史に残っているのだねぇ。文学史上のトピックとして残るのはいいけれど、だけど、これって再版し残す価値ある内容だろうか?
私は田山花袋に声を大にして言いたい。
チラシの裏に書いておけ、このばか者!!
近代ブンガクの落とし穴にはまった感じ。
文学史に興味がないのでよく知らなかったのだけれど、自然主義ってなんなんだ?赤裸々、告白、暴露のことか。
もう、ほんと脱力した。
そりゃ、当時の人はさぞかし吃驚したろうと思う。書いた者勝ちだね。作品の、いままで誰も書かなかった「スタイル」だけで、文学史に残っているのだねぇ。文学史上のトピックとして残るのはいいけれど、だけど、これって再版し残す価値ある内容だろうか?
私は田山花袋に声を大にして言いたい。
チラシの裏に書いておけ、このばか者!!
買ってしまうかもしれない。
まだ読んでいない本はこの世に星の数ほどあるけれど、ほんとうに読んでおきたいと思う言葉は古典にすべて揃っているだろう。
これ「一冊」で青空文庫を読むだけでもいいかもしれない。青空文庫でさえ読み終えるにはもう時間が足りないかもしれないのだから。
まだ読んでいない本はこの世に星の数ほどあるけれど、ほんとうに読んでおきたいと思う言葉は古典にすべて揃っているだろう。
これ「一冊」で青空文庫を読むだけでもいいかもしれない。青空文庫でさえ読み終えるにはもう時間が足りないかもしれないのだから。
図書館の本が、実はあまり好きではない。
あの、本を保護するために掛けてあるブッカーが嫌だ。本を手に取ったときの紙の感触が失われているし、本が息苦しそうだ。最近は蔵書バーコードなどが貼ってあって美しくない。
自宅と仕事先のどちらにも、歩いて5分くらいの近所に図書館がある。
なのでちょくちょく利用しているのだけれど、利用しといて言うのもなんだけれども、図書館を使うようになって、なんだかくだらない読書が多くなってしまった気がしている。
書店で見かけたのであれば、手にとってぱらぱらとページを繰って拾い読みして、ほんとうに読みたいと思った本だけを買って帰ってわくわくしながら大事に読んでいた。図書館の本は、とりあえず借りてしまう。とりあえずソファに座って読み始めてしまう。吟味しなくなった。
結果、金額に値しない本に読書の時間を使っていることも多くなった。無料の、暇潰しの読書。
以前住んでいた街にあった貸本屋の100円でも、読みたい本かどうかもっと楽しく迷っていたと思う。
代価を支払うというのは大事なことだ、と思った。
あの、本を保護するために掛けてあるブッカーが嫌だ。本を手に取ったときの紙の感触が失われているし、本が息苦しそうだ。最近は蔵書バーコードなどが貼ってあって美しくない。
自宅と仕事先のどちらにも、歩いて5分くらいの近所に図書館がある。
なのでちょくちょく利用しているのだけれど、利用しといて言うのもなんだけれども、図書館を使うようになって、なんだかくだらない読書が多くなってしまった気がしている。
書店で見かけたのであれば、手にとってぱらぱらとページを繰って拾い読みして、ほんとうに読みたいと思った本だけを買って帰ってわくわくしながら大事に読んでいた。図書館の本は、とりあえず借りてしまう。とりあえずソファに座って読み始めてしまう。吟味しなくなった。
結果、金額に値しない本に読書の時間を使っていることも多くなった。無料の、暇潰しの読書。
以前住んでいた街にあった貸本屋の100円でも、読みたい本かどうかもっと楽しく迷っていたと思う。
代価を支払うというのは大事なことだ、と思った。
ニュージーランド産のリンゴをふたつ、買った。
日本の「ふじ」なんかに比べると、小ぶりで、ころんとしていて、このセザンヌのリンゴみたい。
リンゴは大好きで、フルーツとしてというよりジャガイモ、玉ネギ・・の続きにある食材と言う感じで一年中食べているのだけど、4月くらいになるとどうしても味がぼけてくるのが残念だった。春になったら南半球のリンゴを輸入すればいいのにと思っていた。日本の農家は保護されているから輸入されないのかな?オレンジのときも大騒動だったしなぁ、なんて思ってたので、昨日、寄った八百屋ではじめて見てさっそく購入。
美味しい。甘味は充分、酸味も程好い。
なにより歯ざわりが好みだ。リンゴは、カリッ!ってくらいのが好きだ。サクでもシャリでもダメ。断然、カリッ!
過保護じゃなく育った果実という風で、とても気に入った。
ちょっと検索したら、ニュージーランド産のリンゴは平成5年に輸入解禁されているって。えー?そうだったの?知らなかった。加工用?
普通にスーパーに並んでたかなぁ?
日本の「ふじ」なんかに比べると、小ぶりで、ころんとしていて、このセザンヌのリンゴみたい。
リンゴは大好きで、フルーツとしてというよりジャガイモ、玉ネギ・・の続きにある食材と言う感じで一年中食べているのだけど、4月くらいになるとどうしても味がぼけてくるのが残念だった。春になったら南半球のリンゴを輸入すればいいのにと思っていた。日本の農家は保護されているから輸入されないのかな?オレンジのときも大騒動だったしなぁ、なんて思ってたので、昨日、寄った八百屋ではじめて見てさっそく購入。
美味しい。甘味は充分、酸味も程好い。
なにより歯ざわりが好みだ。リンゴは、カリッ!ってくらいのが好きだ。サクでもシャリでもダメ。断然、カリッ!
過保護じゃなく育った果実という風で、とても気に入った。
ちょっと検索したら、ニュージーランド産のリンゴは平成5年に輸入解禁されているって。えー?そうだったの?知らなかった。加工用?
普通にスーパーに並んでたかなぁ?
22時を過ぎて庭に出たら、東の空に月が煌々と輝いていた。今夜の月は立待月。ほんとうに呆れるくらいに煌々としている。
この明るさは太陽の光を反射しているのだよなぁ・・と考えながら、ふと、月の周りの漆黒を見た。そこには太陽の光を遮るものがなぁーんにもないんだってことに気がついて、どきりとする。
煌々と輝く月のすぐそばから広がる無。怖くなった。
この明るさは太陽の光を反射しているのだよなぁ・・と考えながら、ふと、月の周りの漆黒を見た。そこには太陽の光を遮るものがなぁーんにもないんだってことに気がついて、どきりとする。
煌々と輝く月のすぐそばから広がる無。怖くなった。
DREAMS COME TRUE
2012年6月1日 日常夢はなんですか?
この質問にまともに答えられたためしがない。
そもそも夢ってなんだろう。辞書を引いてもなんだかぴんと来ない。
夢、夢・・私の夢ってなんだろう?と途方に暮れてしまうし、「夢はなんですか?」なんて、なんでそんな気恥ずかしいことを訊くんだろうと思ってしまう。
子供の頃の夢を次々に実現させたランディ・パウシュが「最後の授業」の中で言っている。
壁は夢の実現を阻むものではなくて、あなたの思いの強さを知るためのものだ、というようなことを。
私には、思いの強さがたりないんだろう。なににつけ。
どうしても欲しい、なりたい、体験したい、そういうのなかったな。いまもないな。
だから、一生懸命頑張って壁を乗り越えたということがない。ちょこっと助走をつければ飛び越えられる程度の壁しか選ばなかったんだな。2度試して、それで越えなければ他へ行く、それで構わない。
夢につきものの、悔しい羨ましいという感情が苦手だ。この感情とは無縁で暮らしたい。
夢は何かと問われたら、隠遁生活と答えるしかないか。面接は落ちるね。
この質問にまともに答えられたためしがない。
そもそも夢ってなんだろう。辞書を引いてもなんだかぴんと来ない。
夢、夢・・私の夢ってなんだろう?と途方に暮れてしまうし、「夢はなんですか?」なんて、なんでそんな気恥ずかしいことを訊くんだろうと思ってしまう。
子供の頃の夢を次々に実現させたランディ・パウシュが「最後の授業」の中で言っている。
壁は夢の実現を阻むものではなくて、あなたの思いの強さを知るためのものだ、というようなことを。
私には、思いの強さがたりないんだろう。なににつけ。
どうしても欲しい、なりたい、体験したい、そういうのなかったな。いまもないな。
だから、一生懸命頑張って壁を乗り越えたということがない。ちょこっと助走をつければ飛び越えられる程度の壁しか選ばなかったんだな。2度試して、それで越えなければ他へ行く、それで構わない。
夢につきものの、悔しい羨ましいという感情が苦手だ。この感情とは無縁で暮らしたい。
夢は何かと問われたら、隠遁生活と答えるしかないか。面接は落ちるね。
嫌いだ。
と思うエネルギーってどうしようもなく自分自身を蝕むね。
どんどんどんどん、気持も身体も重たくなってくる。
船底に厚くこびりついたフジツボみたいだ。これのせいで軽やかに滑らかに波を切って進めない。
いまは、進むこともしないで波のうねりに揺られているだけ。嗚呼。
ほんとうに、ロンダリングのお仕事ないだろうか。
物件と一緒に私自身のロンダリングもしたいわ。
誰にも会いたくない。
いちにち、ひとことも喋らずに過ごしたい。
ひとりになりたい。
と思うエネルギーってどうしようもなく自分自身を蝕むね。
どんどんどんどん、気持も身体も重たくなってくる。
船底に厚くこびりついたフジツボみたいだ。これのせいで軽やかに滑らかに波を切って進めない。
いまは、進むこともしないで波のうねりに揺られているだけ。嗚呼。
ほんとうに、ロンダリングのお仕事ないだろうか。
物件と一緒に私自身のロンダリングもしたいわ。
誰にも会いたくない。
いちにち、ひとことも喋らずに過ごしたい。
ひとりになりたい。
「東京ロンダリング」
2012年5月8日 日常
事故物件に住んで物件をロンダリングする仕事・・というアイデアを思いついたら、作家なら「いける!」と思っちゃうよね。
というわけで、そのアイデアだけの、ゆる~い再生物語。
小説自体はもう読み捨てる感じだけれど、ただ住むことだけを仕事にして家賃はタダ、幾ばくかの報酬を得て3ヶ月ごとに部屋を転々とする、それちょっとやってみたいかも、なんて思った。
短期間で移り住むことを前提にしたら、どうしても必要なモノ、絶対持って行きたいモノってなんだろう、と考えてしばし遊んだ。
いろんな街に流れ者のように住むというのも魅力的だ。本物の流れ者になんかなれっこないから、食う寝るが保証されてなら願ったり叶ったり。事故物件云々は置いといて、だけどね。
というわけで、そのアイデアだけの、ゆる~い再生物語。
小説自体はもう読み捨てる感じだけれど、ただ住むことだけを仕事にして家賃はタダ、幾ばくかの報酬を得て3ヶ月ごとに部屋を転々とする、それちょっとやってみたいかも、なんて思った。
短期間で移り住むことを前提にしたら、どうしても必要なモノ、絶対持って行きたいモノってなんだろう、と考えてしばし遊んだ。
いろんな街に流れ者のように住むというのも魅力的だ。本物の流れ者になんかなれっこないから、食う寝るが保証されてなら願ったり叶ったり。事故物件云々は置いといて、だけどね。
逆説19’33” 輪切りにされる脳のための磁気共鳴変奏曲
2012年5月4日 日常 コメント (2)というわけでMRI。
1階から上の、木材をふんだんに使った内装の柔らかさとうらはら、地下1階のそこは分厚そうな金属の扉が5つ並ぶコンクリート打ちっぱなしの寒々しい空間。扉の開閉は太い回転式のレバーで、大型金庫のよう。ふと、火葬場の窯を思い浮かべてしまったけれど、あそこのほうがまだ内装に儀式的な配慮があった気がする。
コンクリ越しに鳴り響くノイズ。
ゴウンゴウンゴウンゴウンガガガガガガガガゴンゴンゴンゴンキーンキーンキーン・・・・。
なんとも禍々しい轟音。
扉の前の待合に流れるイージーリスニングのもの凄い違和感に笑いそうになる。
呼ばれて入った部屋は白く輝いて、ふた昔前のSF映画のセットのよう。ベッドに寝て頭を固定され、格子に組んだ覆いが被せられる。イメージは、「羊たちの沈黙」で移送されるレクター博士だ(笑)。
そして約20分、「不確定性の音楽」を大音響で聴かされて終了。痛くも痒くもなかったけれども、難聴気味の耳にいいのこれ?
検査結果はまた来週。
1階から上の、木材をふんだんに使った内装の柔らかさとうらはら、地下1階のそこは分厚そうな金属の扉が5つ並ぶコンクリート打ちっぱなしの寒々しい空間。扉の開閉は太い回転式のレバーで、大型金庫のよう。ふと、火葬場の窯を思い浮かべてしまったけれど、あそこのほうがまだ内装に儀式的な配慮があった気がする。
コンクリ越しに鳴り響くノイズ。
ゴウンゴウンゴウンゴウンガガガガガガガガゴンゴンゴンゴンキーンキーンキーン・・・・。
なんとも禍々しい轟音。
扉の前の待合に流れるイージーリスニングのもの凄い違和感に笑いそうになる。
呼ばれて入った部屋は白く輝いて、ふた昔前のSF映画のセットのよう。ベッドに寝て頭を固定され、格子に組んだ覆いが被せられる。イメージは、「羊たちの沈黙」で移送されるレクター博士だ(笑)。
そして約20分、「不確定性の音楽」を大音響で聴かされて終了。痛くも痒くもなかったけれども、難聴気味の耳にいいのこれ?
検査結果はまた来週。
玄関の脇の、株立ちのモミジに若葉が戻った。
瑞々しい萌黄色の新芽には、秋の紅葉を予感させるような紅が滲んでいて、葉の下にそっと咲く小さな花も濃い紅色で可愛らしい。花が終わると柔らかな緑の掌をいっぱいに開いて薫風に踊りだす。
去年の今頃。
庭仕事を終えた父とふたりで、夕陽を浴びて風にそよぐモミジを眺めていた。
ああ、なんて・・・
「きれいだなぁ」
言葉にしたのは父だった。
一日いちにち、朝と夕とで繊細に優雅にダイナミックに変化する生命力が華やかな、美しい樹。我が家の守り木。
今年も、春モミジが風に揺れている。
庭のすべての草木に緑がもどった。父だけがいない。
瑞々しい萌黄色の新芽には、秋の紅葉を予感させるような紅が滲んでいて、葉の下にそっと咲く小さな花も濃い紅色で可愛らしい。花が終わると柔らかな緑の掌をいっぱいに開いて薫風に踊りだす。
去年の今頃。
庭仕事を終えた父とふたりで、夕陽を浴びて風にそよぐモミジを眺めていた。
ああ、なんて・・・
「きれいだなぁ」
言葉にしたのは父だった。
一日いちにち、朝と夕とで繊細に優雅にダイナミックに変化する生命力が華やかな、美しい樹。我が家の守り木。
今年も、春モミジが風に揺れている。
庭のすべての草木に緑がもどった。父だけがいない。
病院に行くと病気になるから嫌だな、と父が言っていた。
私は、みつけて治してもらうんだからいいのよー、などと笑って聞いていたけど。
突発性難聴の治療のあと、聴力はほぼ戻ったのだけれど、ふわふわとした眩暈が治まらず、耳鼻科、内科、脳神経科のある総合病院を受診した。
年齢的に体質の変わり目でもあるし、昨年はいろいろあって疲れが今頃出てるのかもしれないし、本調子じゃなくても不思議じゃないけど、こじらせるのも嫌だし・・とそんな感じで受診した。
ここ半年の眩暈や不調のことを話し、来週、脳のMRIを撮ることになった。2月の終わりに、右腕に酷い痺れを感じた日が何日かあって、それを話したら「軽い脳梗塞があったかもしれないね」と言われて検査することになった。
ここまで、予想通りの展開なのだった。
浮動性の眩暈について調べたら、メニエール病とか脳幹や小脳の梗塞の可能性について書かれていて、MRIもやっておきたいなと思い、だから総合病院に行ったのだから。
まったく想定内の展開だと言うのに、医者に脳梗塞という単語を使われたら、なんだかすっかり脳梗塞患者になってしまった。
可能性だし、念のための検査だし、小さな梗塞は起きてもそのまま通り過ぎてしまうことも多く、それくらいヒトの身体は上手くできているということも調べ済みなのに。
なのに、気分はすっかり脳梗塞で、なんだか眩暈も昨日までより酷くなったような気がしてしまうのだった。
病院へ行くと病人になるのだ。
気分はすっかりノーコーソクなので、MRIが終わるまで家事はがっつりサボる予定(笑)。初MRI自体はなんだか楽しみなのだ。
私は、みつけて治してもらうんだからいいのよー、などと笑って聞いていたけど。
突発性難聴の治療のあと、聴力はほぼ戻ったのだけれど、ふわふわとした眩暈が治まらず、耳鼻科、内科、脳神経科のある総合病院を受診した。
年齢的に体質の変わり目でもあるし、昨年はいろいろあって疲れが今頃出てるのかもしれないし、本調子じゃなくても不思議じゃないけど、こじらせるのも嫌だし・・とそんな感じで受診した。
ここ半年の眩暈や不調のことを話し、来週、脳のMRIを撮ることになった。2月の終わりに、右腕に酷い痺れを感じた日が何日かあって、それを話したら「軽い脳梗塞があったかもしれないね」と言われて検査することになった。
ここまで、予想通りの展開なのだった。
浮動性の眩暈について調べたら、メニエール病とか脳幹や小脳の梗塞の可能性について書かれていて、MRIもやっておきたいなと思い、だから総合病院に行ったのだから。
まったく想定内の展開だと言うのに、医者に脳梗塞という単語を使われたら、なんだかすっかり脳梗塞患者になってしまった。
可能性だし、念のための検査だし、小さな梗塞は起きてもそのまま通り過ぎてしまうことも多く、それくらいヒトの身体は上手くできているということも調べ済みなのに。
なのに、気分はすっかり脳梗塞で、なんだか眩暈も昨日までより酷くなったような気がしてしまうのだった。
病院へ行くと病人になるのだ。
気分はすっかりノーコーソクなので、MRIが終わるまで家事はがっつりサボる予定(笑)。初MRI自体はなんだか楽しみなのだ。
放ったらかしガーデナーの私のベランダも、地味に花盛りだ。
2年目のムスカリの青、3年目のラベンダーとローズマリーの薄紫、去年挿し芽をしたランタナの薄いピンク。
それにプランターに溢れんばかりのハコベのちいさな白花。
ハコベは、ある日気がついたらわっさわさに生えていた。昨年、ゴーヤが終わって古土を篩いにかけてプランターに入れベランダの隅に置いていた。そのプランターがハコベに席巻されていた。
蔓延るハコベ。お見事。
ハコベって漢字では繁縷って書くのね。生い茂る茎っていう意味らしい。見たまんまそのまんまね。可笑しい。
さて。ハコベの種が古土の中で眠っていたというのは判るのだけど、ベランダの水桶のタニシはいったいどこから来たんだろう?
昨夏にベランダの水遣り用に桶を置いた。2階に水道はないので庭のホースを時々ベランダに上げて水を溜めている。その桶に小さなちいさなタニシが数匹。雨雲に乗って来たの?
ゴミが入らないよう目の細かいネットを掛けてあるし、不思議ふしぎ。
2年目のムスカリの青、3年目のラベンダーとローズマリーの薄紫、去年挿し芽をしたランタナの薄いピンク。
それにプランターに溢れんばかりのハコベのちいさな白花。
ハコベは、ある日気がついたらわっさわさに生えていた。昨年、ゴーヤが終わって古土を篩いにかけてプランターに入れベランダの隅に置いていた。そのプランターがハコベに席巻されていた。
蔓延るハコベ。お見事。
ハコベって漢字では繁縷って書くのね。生い茂る茎っていう意味らしい。見たまんまそのまんまね。可笑しい。
さて。ハコベの種が古土の中で眠っていたというのは判るのだけど、ベランダの水桶のタニシはいったいどこから来たんだろう?
昨夏にベランダの水遣り用に桶を置いた。2階に水道はないので庭のホースを時々ベランダに上げて水を溜めている。その桶に小さなちいさなタニシが数匹。雨雲に乗って来たの?
ゴミが入らないよう目の細かいネットを掛けてあるし、不思議ふしぎ。
愛媛から朝掘り筍が届く。
届いてしまったらさあ、待ったなし。
皮を剥く、剥く、剥きまくる。家で一番大きな鍋をふたつ、2口しかないコンロに乗せて茹でる茹でる茹でまくる。
筍10本は、さすがに食べきれない。茹でながら知り合いに電話をかけまくって強引にお裾分け。
というわけで、今夜は筍づくし。
筍ごはん、酢味噌和え、土佐煮、焼き筍。
新鮮なので焼き筍がほっくりと食感も香りも良くて美味しかった。
明日は天麩羅ときんぴら。
明後日はチンジャオロースかな?
届いてしまったらさあ、待ったなし。
皮を剥く、剥く、剥きまくる。家で一番大きな鍋をふたつ、2口しかないコンロに乗せて茹でる茹でる茹でまくる。
筍10本は、さすがに食べきれない。茹でながら知り合いに電話をかけまくって強引にお裾分け。
というわけで、今夜は筍づくし。
筍ごはん、酢味噌和え、土佐煮、焼き筍。
新鮮なので焼き筍がほっくりと食感も香りも良くて美味しかった。
明日は天麩羅ときんぴら。
明後日はチンジャオロースかな?
「女は下着でつくられる」
2012年4月13日 読書
昭和のヨーコさんたちはほんとうに元気だ。
サノ・ヨーコ、オノ・ヨーコ。この人もまたヨーコさんだ。
鴨居羊子。
日本ではじめてカラー下着を作ったひとだって。「スキャンティ」というのもこのヨーコさんの命名だって。へぇー知らなかった。
でもほんとうに元気だ。
追い風に乗り、向かい風に胸を張り、ずいずい、えいやっっと進んでいく勢いのようなものを感じる。このヨーコさんも若かったし、ほかのヨーコさんたちも、それから時代もまた若かったのだと思う。
眩しいように目を細めてヨーコさんの文章を読む。そうね、眩しい。羨ましいではない。この時代に生まれても私はヨーコさんではなかったろうから。
老成、いやたんに年老いた平成、という時代に生きるワタシは、若く瑞々しいヨーコさんに元気な気分だけもらってゆく。
サノ・ヨーコ、オノ・ヨーコ。この人もまたヨーコさんだ。
鴨居羊子。
日本ではじめてカラー下着を作ったひとだって。「スキャンティ」というのもこのヨーコさんの命名だって。へぇー知らなかった。
でもほんとうに元気だ。
追い風に乗り、向かい風に胸を張り、ずいずい、えいやっっと進んでいく勢いのようなものを感じる。このヨーコさんも若かったし、ほかのヨーコさんたちも、それから時代もまた若かったのだと思う。
眩しいように目を細めてヨーコさんの文章を読む。そうね、眩しい。羨ましいではない。この時代に生まれても私はヨーコさんではなかったろうから。
老成、いやたんに年老いた平成、という時代に生きるワタシは、若く瑞々しいヨーコさんに元気な気分だけもらってゆく。
落ち葉を掃くのが面倒だからって、木を幹から切ってしまうというそういうガサツさが嫌だ。枝の落とし方にだってやりようというものがあるはずだ。樹形は悪くなるけれども隣家に張り出した枝を間引けばいいではないか。ついでのように、ヤケクソのように枝を落とされた姫辛夷は春になって桜も満開だというのにまだ丸裸だ。夏に大きな葉が木陰を作ってくれて、さわやかな葉擦れの音をたててくれるこの木が大好きなのに。この冬、姫辛夷の木を見るたびため息が出た。どうしてこういう無残な真似をするのだろうと、ずっと腹立たしかったんだ。
姫辛夷の大きな木が、一輪だけ花を咲かせていた。
太い幹から伸びた細枝の先に一輪だけ。
この一輪に気付けよ。
姫辛夷の大きな木が、一輪だけ花を咲かせていた。
太い幹から伸びた細枝の先に一輪だけ。
この一輪に気付けよ。